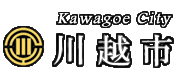県指定有形文化財 三芳野神社社殿及び末社蛭子社・大黒社 付明暦二年の棟札1枚
最終更新日:2023年9月4日

三芳野神社社殿

三芳野神社蛭子社

三芳野神社大黒社
| 名称 | 三芳野神社社殿及び末社蛭子社・大黒社 付明暦二年の棟札1枚 |
|---|---|
| よみ | みよしのじんじゃしゃでんおよびまつしゃえびすしゃ・だいこくしゃ つけたりめいれきにねんのむなふだ1まい |
| 種別 | 県指定有形文化財・建造物 |
| 員数 | 3棟 |
| 所在地 | 郭町2-25-11 |
| 指定年月日 | 昭和30年11月1日 |
| 所有者 | 三芳野神社 |
| 文化財の概要 | 当社は川越城本丸内に位置し、江戸時代は仙波東照宮と共に幕府の手厚い保護を受けた神社となり、川越を代表する神社である。現在の建物は、本殿と拝殿が幣殿で結ばれた複合社殿(権現造)の形式になっているが、慶安2年(1649)松平信綱が奉納した『三芳野天神縁起』に描かれているように、当初は幣殿が存在せず、本殿と拝殿が独立して建っていた。その後明暦2年(1656)に松平信綱が造営奉行となって行われた大規模な修理工事により幣殿が増築され、本殿と拝殿を繋いだ現在の権現造になったとされている。なお、本殿と幣殿には透塀(すきべい)が三方に囲い、拝殿背後の柱に接続している。弘化4年(1847)には、社殿の屋根が柿(こけら)葺から瓦葺に葺き替えられたが、大正11年(1922)に現在の銅板葺に変更されている。社殿に通じる参道には石鳥居が1基あり、境内には末社、手水舎、札所、社務所などの建物や燈籠、石碑などが配されている。本殿は正面3間側面2間の三間社入母屋造で、四周に縁と高欄が回り、正面に木階(きざはし)が付設されて前面が幣殿に接続している。身舎(もや)内部は内外陣に分かれ、内陣正面の柱間3間に板唐戸、外陣正面の中央間に板唐戸、両脇間に蔀しとみぞなえには極彩色が施された蟇股が入っている。幣殿は正面1間側面2間の両りょう下さげ造づくりで、本殿と拝殿を繋ぐ。天井は小組格天井(こぐみごうてんじょう)とし、組物は出三斗、中備は外部が蟇股、内部は間斗束(けんとづか)となっている。拝殿は正面3間側面2間の入母屋造で、背面は幣殿に接続する。三方に縁高欄を回し、正面に1間の向拝を設けている。天井は小組格天井とし、組物は出三斗で、中備は外部が蟇股、内部は間斗束となっている。向拝は大面を取った角柱を陸梁(ろくばり)形の頭貫で繋いで、両端に獅子鼻を付け、連三斗(つれみつど)を組んで中備に蟇股を設けている。裏側には花木を篭彫りにした装飾豊かな手挟(たばさみ)が付設されている。蛭子社本殿と大黒社本殿は、拝殿の前方、参道に向かい合って鎮座する末社で、拝殿に向かって右が蛭子社、左が大黒社である。両社とも一間社流造、見世棚造の簡素な建築である。建築年代は、蛭子社に掲げられている額の背後に享保19年(1734)の年紀があることから、その頃造営されたと考えられる。以上のように、当社は城の守護社として幕府に庇護され、作事方の大工頭や大棟梁が何代にもわたって最高の技術を凝らして修造に携わった建築であり、代表的な近世社寺建築の一つである。 |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086