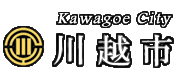中台囃子連中

今福囃子連中
| 名称 |
川越祭りばやし |
| よみ |
かわごえまつりばやし |
| 種別 |
県指定民俗文化財 無形民俗文化財 |
| 所在地 |
中台地区 【中台地図】・今福地区 【中台地図】・今福地区 【今福地図】 【今福地図】 |
| 指定年月日 |
昭和52年3月29日 |
| 所有者 |
中台囃子連中/今福囃子連中 |
| 備考 |
川越では多くの町内に祭りばやしが伝わり、川越市囃子連合会に加盟している囃子連は、令和3年度現在39団体に上っている。それらの大半は、江戸時代後期に伝えられた江戸の囃子がもとになっているとされ、王蔵流・芝金杉流・堤崎流の3流派の系統に大別できる。
中台
中台の祭りばやしは里神楽から発展し、江戸時代後期に高井戸(現杉並区)の笛角と呼ばれる人から指導を受けて祭りばやしの基礎がつくられた。その後明治時代の初めに、松平不昧公お抱えの囃子方であった王蔵金の指導によって、それまでの囃子を刷新したと伝えられ、「王蔵流」と称している。
川越まつりでは、仲町(旧志義町)の山車に乗って囃子方を務めているほか、地元八雲神社の祭礼(4月15日前後の日曜日、8月第1土・日曜日)にも囃子を奉納している。楽器は大太鼓1、小太鼓2、笛1、鉦1で、必ず舞方が付く。
曲目は屋台、鎌倉、鎌倉攻め、宮昇殿、いんば、子守り歌、数え歌、四丁目、大間昇殿である。川越周辺に流派の広がりがあり、市内6ヶ所と市外2ヶ所に直接伝授した。
今福
川越まつりで六軒町の山車に乗って演奏しているのが、今福地区に伝わる祭りばやしである。明治21年(1888)に六軒町が山車を新造した際選ばれて、以来現在までこの付き合いが続けられている。そのほか、地元の菅原神社では4月15日の春祈祷と10月15日の秋祭礼、平野神社では7月中旬の土日曜日(土曜日は宵宮、日曜日は昼間)の天王様でこの祭りばやしが演じられている。
今福の祭りばやしは、中台と一緒であったが、その後五宿(甲州街道にあった5つの宿場の総称、現在の調布市)の下布田(しもふた)囃子の師匠だった福岡仙松の指導を受けて、調子を異にする囃子(新囃子)に変わった。仙松は芝(東京都港区)の古川に架かる金杉橋付近で下駄屋を営んでいたことから、この囃子を「芝金杉流」と称するようになった。
楽器は大太鼓1、小太鼓2、笛1、鉦1、曲目は屋台、宮昇殿、鎌倉、鎌倉攻め、師調舞、トッパトーガク、いんば、子守歌、数え歌、八百屋お七である。なお今福の囃子は、ここからさらに砂新田・寺尾・北山田など市内9地区に伝わり、計10団体で「金杉会」を組織し合同練習などを行っている。 |
| 開催情報 |
《中台》
日時
令和6年8月3日(土曜) 宵宮
1回目 午後5時30分頃から、祭り囃子演奏(約30分程度)
2回目 午後6時45分頃から、祭り囃子演奏(約30分程度)
3回目 午後8時15分頃から、祭り囃子演奏(約30分程度)
令和6年8月4日(日曜) 本祭
1回目 午前8時30分頃から、八雲神社で祭り囃子演奏(短め)
2回目 午前10時15分頃から、中台南自治会館で祭り囃子奉納(約30分程度)
3回目 午前11時30分頃から、中台自治会館で祭り囃子奉納(約30分程度)
4回目 午後0時45分頃から、中台元町自治会館で祭り囃子奉納(約30分程度)
会場
中台八雲神社ほか - 当日は、天候等の事情により中止や日時の変更をする可能性があります。
- 会場までは、公共交通機関をご利用ください。
《今福》
日時
令和6年7月13日(土曜) 宵宮
午後6時頃から午後8時頃まで、今福平野神社で祭囃子を奉納。
会場
今福平野神社(川越市今福1121) - 当日は、天候等の事情により中止や日時の変更をする可能性があります。
- 会場までは、公共交通機関をご利用ください。
|