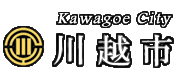県指定有形文化財 川越城本丸御殿及び家老詰所
最終更新日:2023年9月6日

川越城本丸御殿

川越城本丸御殿家老詰所
| 名称 | 川越城本丸御殿及び家老詰所 |
|---|---|
| よみ | かわごえじょうほんまるごてんおよびかろうつめしょ |
| 種別 | 県指定有形文化財・建造物 |
| 員数 | 2棟 |
| 所在地 | 郭町2-13-1 |
| 指定年月日 | 昭和42年3月28日 |
| 所有者 | 川越市 |
| 文化財の概要 | 本丸御殿は、棟札の写によれば、松平斉典が川越城主だった嘉永元年(1848)に竣工した。本来全部で16棟、建坪1025坪の規模を擁していたが明治維新後に解体され、現在までに残っているのは、玄関と大広間の部分だけである。外観は、間口19間奥行5間の横長の大建築で、入母屋造桟瓦葺の大屋根に2間の大唐破風と霧除けの付いた玄関を正面に構え、その両側に瓦葺の櫛形塀を備えている。玄関には式台が設けられ、中に入ると四周を9尺幅の廊下で囲まれた座敷が6室並んでいる。玄関を上がってすぐに配された36畳の大広間は、西側に3間幅の床の間を備え、城郭建築の格式と豪壮さをもっとも強く感じさせる部屋である。明治維新後に少しずつ解体され、わずかに玄関と大広間の部分だけが残された建築遺構ではあるが、近世御殿建築として貴重な建物である。 家老詰所は、明治5年(1872)に福岡村(現ふじみ野市)の星野家に払い下げられていたものを昭和63年度に現在地に復元移築したものである。「本城住居図」(光西寺蔵)により、当初は本丸の西の外れに土塀で囲まれた独立建物だったことがわかっていたが、復元時に約40m東側にずらして現在の位置に配することとなり、本丸御殿につなげて建設された。外観は、寄棟造桟瓦葺屋根の平屋建で、南側に下屋が延びて縁側が回る一般的な住宅建築に見えるが、室内は1間毎に5寸角の柱が立ち、武家住宅の剛健さがうかがわれる。間取りは、西側から床の間床脇付き10畳の主座敷、8畳の次の間2室が続き、南側に縁と畳敷の入側が庭に面して配され、北側にも座敷が張り出し、縁を介して便所が2カ所設けられている。藩政を実質的に支えた家老の居室が残っているのは全国的に珍しく、本丸内の日常生活を知る上で貴重な建築である。 |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086