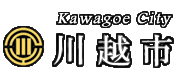県指定有形文化財 黒地小花模様小紋帷子
最終更新日:2024年5月28日

帷子前身全体

家紋部分
| 名称 | 黒地小花模様小紋帷子 |
|---|---|
| よみ | くろじこばなもようこもんかたびら |
| 種別 | 県指定有形文化財・工芸品 |
| 員数 | 1領 |
| 所在地 | 小仙波町1-20-1 |
| 指定年月日 | 平成30年2月27日 |
| 所有者 | 喜多院 |
| 文化財の概要 | 喜多院に伝来した、三つ葉葵の五紋付の小紋の帷子。葵の葉(直径約1.8センチメートル)を軽やかに散らし、葉の間に鐶状(かんじょう)を花びら風に沿わせたかわいい小花模様である。小紋染とは、細かい柄を一色で染めた型染のことで、遠目には無地のようで、近くで見ると繊細な極小の美が広がる。染色法は、まず突彫りの技法で小花模様を型紙に彫り、これを使い生地に防染糊を置き、その後墨や顔料を引き染した後、糊を落としている。染め上りは、模様の輪郭が冴えて表出され、図様も精緻な意匠で、高度な型染の技術が発揮されている。また帷子とは、麻地を単衣仕立てにした夏用の小袖型の衣料をいう。近世初期の小紋染衣料の類例には、最古の作例である上杉神社所蔵《伝上杉謙信所用黄色地小花模様小紋帷子》などが知られている。本品には、この時代の資料と共通して、武将たちに好まれた品格高い小紋染を見ることができる。本品が当寺に伝来した経緯は明らかではない。着用者については、徳川将軍家ゆかりの喜多院に伝来したこと、家紋が三つ葉葵である(葵紋の葉脈の数が多く古様である)こと、図柄には一般に使用されない葵の葉をモチーフにするなど、徳川家の中でも特別な人物であった可能性が高い。このように、本品は、江戸時代初期の小紋帷子として貴重である。身丈136.0センチ、裄61.3センチ。 |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 調査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086