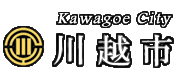国指定重要文化財 大沢家住宅
最終更新日:2023年9月4日

大沢家住宅
| 名称 | 大沢家住宅 |
|---|---|
| よみ | おおさわけじゅうたく |
| 種別 | 国指定重要文化財・建造物 |
| 員数 | 1棟 |
| 所在地 | 元町1-15-2 |
| 指定年月日 | 昭和46年6月22日 |
| 所有者 | 個人 |
| 文化財の概要 | 大沢家住宅は、呉服太物商、西村半右衛門(屋号「近江屋」)が建てたもので、間口6間奥行4間の規模の大きな町家である。明治26年(1893)の大火に焼け残った貴重な建築であり、棟木に打ち付けてある祈祷札及び神棚の墨書から寛政4年(1792)に建設されたことがわかっている。建物は、切妻造桟瓦葺屋根の総二階で、前面に奥行4尺の下屋庇が付く。軒は出桁で支えるが、明治大火後の店蔵と異なり軒蛇腹はなく、2階正面の窓も土塗りの親子格子で構成されており、土蔵造というよりも塗家造の町家といえよう。建築当初は、庇正面だけではなく南面まで廻っていたが、現在は撤去されている。正面の庇は中央間が開放され、左右脇間が腰壁で創建時は庇柱内側に防火戸を立てる構えであった。1階は手前半間通りを土間とし、奥を床上部分とする一室空間で、背面側中央に間口3間奥行半間の神棚を設け、2階へは東南隅の箱階段で登った。1階の戸締まりは、庇との境に入った摺揚戸で行われ、背面は、観音開きの土扉が神棚の両脇に2箇所設けられ、火災の際には住居部分と完全に分離できるようになっている。2階は5室からなり、棟通りで二つに分かれ、正面北側の14畳間には床の間と地袋付きの床脇が備えられている。大沢家住宅は、明治大火後に毅然とした姿で川越商人たちの目前に現出し、土蔵造建築の防火性を実証させた町家であり、川越における土蔵造の町並みが誕生するきっかけをつくった貴重な建築といえる。 |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086