暮らしの移り変わり
みなさんの家には、洗濯機(せんたくき)や炊飯器(すいはんき)など多くの電気で動く道具があると思います。これらがつかわれるようになったのは昭和30年代からです。今まですべて手作業(てさぎょう)であったものを代わりにやってくれる道具の登場は、人々の暮らしを大きく変えることになりました。人々はくふうをかさね、生活はべんりになりました。では、どのようにかわってきたのか調べてみましょう。
身近な人に聞いてみよう
「かま」について、おばあちゃんに聞いてみたよ!
![]()
おばあちゃん、しつもん。かまってなあに?

かまは、お米をたくためにつかったむかしの道具なの。なべよりもふかくて、口がせまいかたちで、むかしは電気がなかったから、かまどで火をおこして使ったんだよ。
![]()
ふ~ん。それで、ごはんは、おいしかった?

おいしかったわよ。お米がおいしくなるくふうがいっぱいあったの。
かまどにかまを入れたとき、羽(はね)という部分で、かまどでおこした火の熱(ねつ)をどこにもにげないようにしていたの。
ふたは、とても厚(あつ)くておもい木でできていて、かまの中の熱をとじこめる役目(やくめ)があったの。お米をむらすのにもちょうどよかったわ。それと、ふたの上にある下駄(げた)の歯(は)のような2本の取(と)っ手は、これでふたのそりをふせいだんだって。
底(そこ)はまるくなっているんだけど、それは熱の伝わりをよくして、お米が全体的(ぜんたいてき)においしくたけるようにしていたのよ。
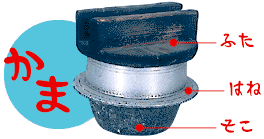
![]()
へー、むかしの道具もすごいのね。

それから電気がつかえるようになって、おばあちゃんの家でも電気がまをかったの。はじめて電気がまをつかったときは、べんりだなあと思ったわ。だって、お米をといで、セットするだけで良かったから。みんなの食事の用意をする時間もみじかくなって、とても楽になったわ。

![]()
そうだったの。おばあちゃんの話、こんど、学校で発表(はっぴょう)してみるね。おばあちゃん、どうもありがとう!

どういたしまして。
むかしの道具について、今の道具とのちがいを調べて、暮らしがどのように変わったか考えてみよう。
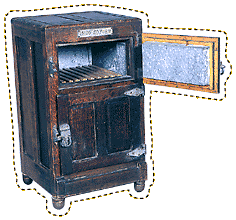
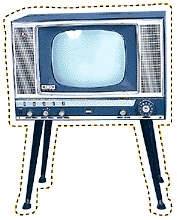
むかしの道具を動かしてみたよ

ちくおんきで音楽を聞くときには、レコードを回転盤(かいてんばん)の上にあわせ、右側(みぎがわ)の取(と)っ手をグルグル回して、レコード針(ばり)をしんちょうにレコードのみぞにあわせます。ほら、どこかで聞いた音楽がながれてきました。何の歌かわかりますか?

このラジオは昭和33年に作られたものです。このラジオはスイッチを入れても音が聞こえるまで少し時間がかかかります。ビデオのさいしょのほうを注意して聞いてみてください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
川越市立博物館 教育普及担当
〒350-0053 川越市郭町2丁目30番地1
電話番号:049-222-5399 ファクス番号:049-222-5396
川越市立博物館 教育普及担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。