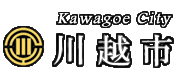【平成25年11月4日】食中毒事件の発生について
最終更新日:2015年1月3日
食中毒事件の発生について
平成25年11月4日
事件の概要
平成25年10月31日午前11時50分頃、市内飲食店を利用した客から「10月30日午後6時頃に市内飲食店を利用し、下痢及び腹痛などの食中毒様症状を呈した。」と川越市保健所に連絡がありました。
川越市保健所では、患者、施設等の調査を行い原因究明に努めてきました。その結果、11月4日、食中毒と断定し、当該営業者に対して3日間の営業停止処分を行いました。
患者の状況
喫食者 :3名(1グループ)
発症者 :3名(1グループ)
症状 :下痢、腹痛等
初発年月日:平成25年10月31日
なお、患者は全員快方に向かっている。
病因物質
ウェルシュ菌
原因施設
川越市内の飲食店
行政処分
処分決定日 平成25年11月4日
営業停止期間 平成25年11月4日から平成25年11月6日
原因施設として決定した理由
1 患者の共通食が、当該施設での食事に限定されていた。
2 患者の主症状及び喫食から発症までの時間が、ウェルシュ菌の主症状と一致していた。
3 患者便を検査したところ、食中毒の原因となるエンテロトキシン産生性ウェルシュ菌が3名中3名検出され、血清型はいずれもHobbs血清型3型であった。
4 患者から回収した当該食事の残品を検査したところ、食中毒の原因となるエンテロトキシン産生性ウェルシュ菌が検出され、血清型はHobbs血清型3型であった。
ウェルシュ菌食中毒について
1.ウェルシュ菌とは
ウェルシュ菌は人や動物の腸管内や土壌、下水などに広く生息している。健康な人の便からも検出されるが、大半は非病原性である。食品では、特に食肉(牛、豚、鶏肉など)の汚染が高く、原因食品も食肉調理加工品が多い。
酸素のないところを好み、環境が悪くなると耐熱性の芽胞を作るため、100℃以上で加熱しても壊れない。このため、給食施設などで食品を大釜などで大量に加熱調理すると、他の細菌が死滅してウェルシュ菌の耐熱性芽胞が残ることがある。
2.症状
潜伏期間は約6から18時間で、ほとんどが12時間以内に発症する。比較的軽度の下痢で発症することが多く、1から2日で回復するものがほとんどである。
嘔吐や発熱等の症状は少なく、予後は良好だが、基礎疾患のある患者や子ども、老齢者では症状が重くなることがある。
3.原因食品・感染源
肉類、魚介類、野菜およびこれらを使用した煮物等。カレー、スープ、シチュー、麺つゆなどを前日に大量調理した後、大鍋のまま室温で放置されていた食品に多くみられる。
4.予防のポイント
(1)前日調理、室温放置は避ける。加熱後できるだけ早く食べる。
(2)一度に大量に調理したときは、小鍋に小分けすると同時に、すばやく冷却するようにする。
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261