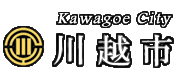ことば・きこえの教室
最終更新日:2021年6月2日
ことばきこえに関する相談は、お気軽にお電話ください。
ことばきこえの教室(049-225-6880)
はじめに
ことばやきこえに課題のある子どもの出生率は,約5パーセントと言われています。
これらの子どもたちの中には,ことばやきこえの課題のために学習上の心配が生じたり,対人関係に悩んだり,集団生活にうまくなじめなかったりする子どもも見られます。
このような子どもたちのために,川越市では昭和46年から,「ことば・きこえの教室」を開設しました。
「ことば・きこえの教室」では
ことばやきこえに課題のある子どもや保護者の相談にのり,一人ひとりに合った指導を行います。そして課題を改善したり,軽減したり,理解したり,受容したりすることにより,子どもたちがよりよい生活と学習ができるように支援します。但し,次のような場合は,対象となりません。ア)小学校の通常学級に在籍していない。
イ)ことばやきこえの課題が,他の障害に起因している。
対象となる子ども
発音に誤りのある子ども
- 「さかな」が「たかな」,「らいおん」が「だいおん」のように違う音になる。
- はっきり発音出来ない音がある。
「きりぎりす」が「ちりじりす」のように唾がたまっているようなはっきりしない音になる。
ことばがつかえる(吃る)子ども
話すときに
- 音やことばを繰り返したり,引き伸ばしたりする。(ぼぼぼぼくは,…)(ぼーくは)
- 最初の音がなかなか出てこない。(……ぼくは)
- 顔の一部に力が入ったり,手足で拍子をとったりする。
聞こえにくい子ども
- 聞き返しや聞き逃しが多い。
- 呼んでも振り向かない。
- テレビの音を大きくしている。
- 医療機関で難聴と診断されている。
通級による指導について
- 週1回決められた曜日時間に通級し,個々の課題に応じた指導を受けます。
- 主に1対1の個別指導を行います。吃音と難聴の児童に対しては,毎学期2回程度のグループ指導をしています。
- 指導効果を高めるために保護者同伴を原則としています。
指導内容
発音に誤りのある子ども(構音障害)
- 正しい音と誤った音を聞き分ける。
- 正しい音が出せるようにする。
- 会話の中でも正しい音が使えるようにする。
ことばがつかえる子ども(吃音)
- 和やかな雰囲気の中で,楽しく会話をする。
- 音読の練習などを通して,読むことや話すことに自信がもてるようにする。
- 遊びを通して共感的関係を作り,積極的に行動できるようにする。
きこえにくい子ども(難聴)
- 定期的に聴力を測り,聴力の管理を行う。
- 会話や日記,体験的な学習を通して,ことばやコミュニケーションの力をつける。
- 聞こえにくさを補うため,必要に応じて,教科の指導も行う。
- 難聴児の仲間作りや障害の理解を図る。
(注)なお,吃音と難聴に関しては,年間3回から4回程度保護者会を行います。
指導開始から終了まで
指導開始
相談の申し込み
保護者が在籍校の担任に相談します。その後「リベ-ラ」(教育センター分室)を経由してことばきこえの教室に連絡が入ります。
相談日時の決定
ことば・きこえの担当より保護者宅に電話をします。この電話で相談日時が決定します。
相談の内容
ア)相談の際に簡単な検査をし,担当は改善指導の必要性の有無を判断します。
イ)保護者は,担当の意見を参考に,改善指導(通級)を希望するかどうかを決めます。
ウ)改善指導を希望する保護者には,担当が通級時間や曜日に関する都合を伺います。
(注)指導は授業時間内となります。
通級指導の開始
ア)対象児童の入級の可否は,川越市教育委員会の就学支援委員会で正式に決定されます。
イ)担当から保護者に通級指導開始に関する連絡が入ります。(指導時間・曜日・準備などについて)
ウ)指導は,入級が決定した次学期から開始します。
指導終了
課題が改善された場合の他,卒業,転出,家の都合等で通級することができなくなった場合も指導は終了となります。
市の教育委員会の就学支援委員会において退級が決定するとその学期で指導終了となります。
問い合わせ
電話:049-225-6880(川越小学校ことば・きこえの教室直通)
(注)指導中は、留守電にて対応していますので,お名前・電話番号・お問い合わせの内容等を入れておいていただくと,こちらからお電話をさせていただきます。
ことばきこえだより
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ