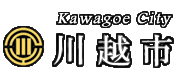冬に流行する子どもの感染症
最終更新日:2023年9月21日
冬に乳幼児がかかりやすい感染症には、以下のようなものがあります。
正しい知識を身につけ、あわてずに対処しましょう。
多くの感染症は薬を飲んだりすることで自然と回復していきますが、重症化する恐れもあります。
重症化の兆しがみられたら、すぐにかかりつけ医に相談して下さい。
感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎)
乳幼児に多い感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎)の原因になるウイルスには、ロタウイルスやノロウイルスなどがあります。
ロタウイルス感染症は3歳未満の乳幼児が中心で、ノロウイルス感染症はすべての年齢層でみられます。
特に冬季に好発します。
《症状》
発熱、吐き気・嘔吐、下痢(黄色より白色調であることが多い)
《合併症》
けいれん、肝炎、まれに脳症
《潜伏期間》
1から3日
《感染経路》
感染患者からの経口感染、飛沫感染、接触感染
《症状持続期間》
ロタウイルス感染症では約5から6日、ノロウイルス感染症では約1から3日
《治療》
ウイルス自体に効く薬はなく、こまめな水分補給で脱水症状を防ぎながら状態の回復を待つしかありません。
下痢止めなどの薬は、体の中にウイルスを留め、回復を遅らせることがあるので、自己判断での服用は避けて下さい。
脱水症状がひどい場合には輸液の治療が行われます。
《拡大防止》
嘔吐物や排泄物の処理は乾燥しないうちに行い、汚染された場所の消毒も忘れずに行って下さい。作業時はマスクとビニール手袋、エプロンを着用するようにしましょう。
症状が消失した後もウイルスの排泄は2週間から1か月ほど続くので、便とおむつの取り扱いに注意して下さい。
《予防》
手洗い、食品の加熱(85度以上で1分以上加熱)、調理器具等の殺菌消毒
インフルエンザ
毎年冬季に流行がみられています。インフルエンザウイルスにはA・B・Cの3つの型がありますが、通常流行するのはA型です。昨年大流行した新型インフルエンザもA型インフルエンザのひとつです。
《症状》
突然の高熱、咽頭痛、鼻汁、悪寒、頭痛、筋肉痛など
《合併症》
肺炎、中耳炎、熱性けいれん、脳症
《潜伏期間》
1から7日(平均2日)
《感染経路》
飛沫感染、接触感染
《症状持続期間》
発熱は3から4日程度、約1週間ほどで症状は軽快します。
発症後48時間以内に抗ウイルス薬の服用を開始すれば、症状の軽減と罹病期間の短縮が期待できます。
《治療》
抗ウイルス薬の投与、発熱や咳などへの対症療法
《拡大防止》
発症後2から5日間はウイルス排泄が続きます。
咳などの症状がある場合は、マスクを着用して下さい。
《予防》
手洗い、咳エチケットの励行、湿度の保持
ワクチン接種
RSウイルス感染症
冬季(12月がピーク)に上・下気道感染を引き起こす代表的ウイルスです。感染力が強く、免疫ができにくいため繰り返し感染しますが、年齢が長ずるに従って徐々に免疫ができて症状は軽くなります。
《症状》
発熱、鼻汁、咳嗽、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、呼吸困難
《合併症》
乳児早期(6か月未満)では、細気管支炎や肺炎にまで進み、入院が必要となる場合があります。
《潜伏期間》
2日から1週間(通常4から5日)
《感染経路》
飛沫感染、接触感染
《症状持続期間》
通常7から12日
《治療》
対症療法。必要に応じて気管支拡張剤、去痰剤などを用います。
《拡大防止》
初感染の場合、発症後7から10日はウイルスが気道分泌物に存在します。
環境表面でかなり長い時間生存できるので、患者と接触した物品類に触れた後は手洗いを行うようにして下さい。
《予防》
手洗い、咳エチケットの励行
ハイリスク児(早産児、先天性心疾患、慢性肺疾患を有する児)に対し、モノクローナル抗体(シナジス)を投与
水痘(みずぼうそう)
冬から春にかけて発生が多く、罹患年齢のほとんどが9歳以下となっています。
《症状》
発疹(体幹から全身に広がっていき、紅斑から水疱、痂皮の順に変化する。かゆみが強い。)
発熱(小児では軽度のことが多い)
《合併症》
皮膚の細菌感染症、肺炎
《潜伏期間》
2から3週間
《感染経路》
空気感染、飛沫感染、接触感染
《症状持続期間》
5から10日
《治療》
対症療法。
新生児水痘、あるいは免疫抑制状態にある患者及び重症例にはアシクロビルなどの抗ウイルス薬が投与されます。
《拡大防止》
感染力は極めて強いです。患者との接触後72時間以内にワクチンを接種することで発症の予防、症状の軽減が期待できます(緊急接種)。
《予防》
ワクチン接種(任意接種)
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎
小児(5から15歳)が最も頻回に罹患する細菌性感染症のひとつです。
《症状》
突然の咽頭痛、発熱、倦怠感、頭痛。小児では、嘔吐、悪心、腹痛がしばしばみられる。
《合併症》
中耳炎、化膿性関節炎、リウマチ熱、急性糸球体腎炎など
《潜伏期間》
2から4日
《感染経路》
飛沫感染、経口感染
《症状持続期間》
3から7日
《治療》
抗菌薬の内服。症状が治まっても、医師の指示通りに飲み続けることが重要です。
《拡大防止》
患者との濃厚接触を避けることが最も重要です。手洗い、うがいなどの一般的な予防法も重要です。
《予防》
手洗い、うがいなどの一般的な予防法の励行。
リンク情報
・埼玉県内の感染症の流行情報はこちら→![]() 埼玉県感染症情報センターホームページ(外部サイト)
埼玉県感染症情報センターホームページ(外部サイト)
関連情報
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108