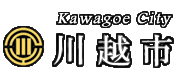市指定有形文化財 木造獅子狛犬
最終更新日:2023年11月9日

| 名称 | 木造獅子狛犬 |
|---|---|
| よみ | もくぞうししこまいぬ |
| 種別 | 市指定有形文化財 彫刻 |
| 員数 | 1対 |
| 所在地 | 小仙波町1-21-1 |
| 指定年月日 | 平成23年2月21日 |
| 所有者 | 仙波東照宮 |
| 備考 | この獅子・狛犬像は、東照宮再建時に奉納されたものと考えられ、現在幣殿に安置されている。本殿に向かって右の口をあけた阿形(あぎょう)が獅子、左の頭部に角があり口を閉じた吽形(うんぎょう)が狛犬である。像高は、獅子が55.2センチメートル、狛犬が62.2センチメートル、寄木造、玉眼、ベンガラ漆地に金泥彩(後補、元は朱漆地に漆箔)からなり、たてがみや脚部の房毛、尾は白土地に緑色、口内は赤色の彩色が施されている。 |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086